大嫌いだった父へ
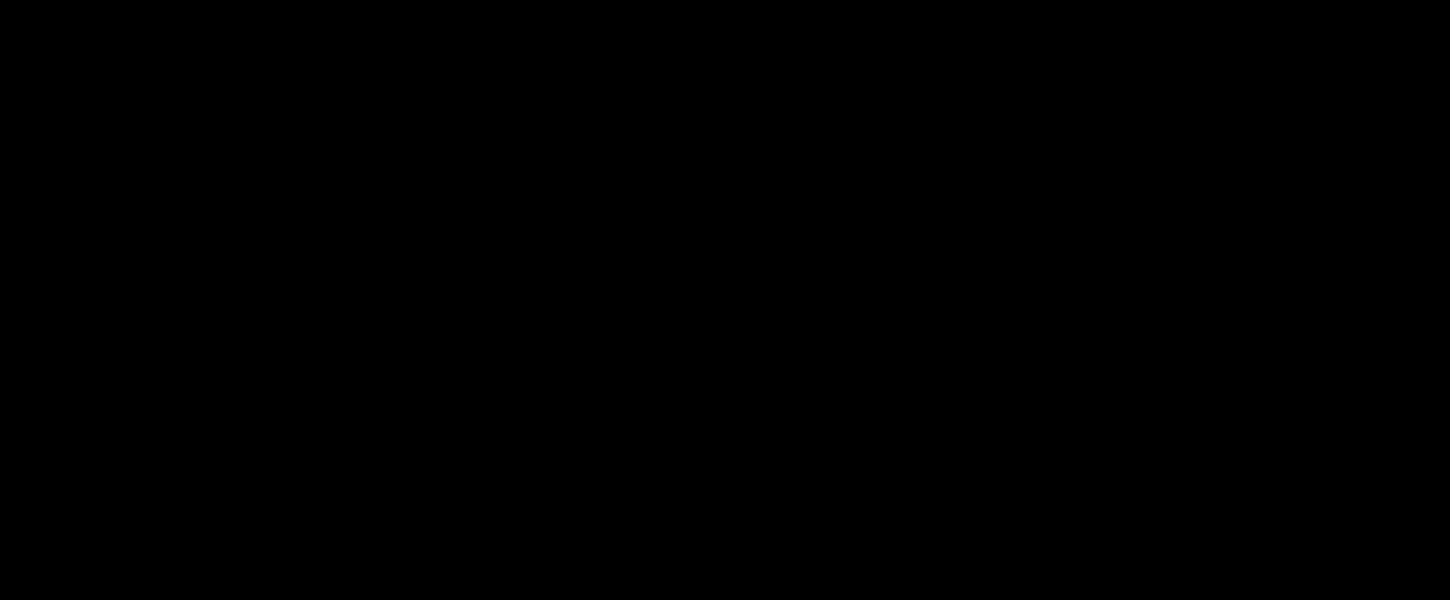
「早く死んでくれ!」
父を見舞った帰り道、何度もこの悪魔のような考えが頭をよぎった。
子どものころから、父はこわい人だった。
よく外で深酒をして早朝に帰宅しては、寝ている私を起こし、態度が悪いと怒られた。
酔った勢いに任せて、子供部屋のドアを殴り、大きな穴を開けられたこともある。
そのころ姉は下宿していたので、私と母は二人きりだった。
母と二人で子供部屋の隅で膝を抱え、父の怒りの嵐が過ぎるのを待った夜もある。
たまに早く家に帰ってくると、いばり散らし、ちょっとしたことで不機嫌になる。
いい子にして、ご機嫌をとり、怒らせないように気をつけた。
私は大人になり、父も歳をとり、ずいぶん穏やかになったように思っていた。
物理的な距離もあり、年に数回会うだけになった親子関係は、よくもないが悪くもなかった。
それが、母の急死により状況が一変した。
家族の一大事を共に乗り切らなくてはならないのに、父は自分のことしか頭になかった。
「俺はどうするんだ」
「お前らは俺が不自由のないようにしろ」
最初は姉と交代で片道3時間をかけて実家に通って父の身の回りのことを世話した。
その頃、父は杖はついていたものの、深刻な身体の不自由はなかった。
それでも家から一歩も出ることはなく、誰かが訪ねてきても階下の玄関まですら降りない。
私も姉も自分たちの仕事も生活もあるため、父が求める「不自由のない暮らし」を実現できず、
私は自分の家に引っ越してきてくれないかと父に相談した。
すると父は激昂し、私を怒鳴りつけ、酒瓶が飛んできた。
訳がわからなかった。私にとっては「父のため」の大きな決断だったのに。
その時掴まれた手首のアザはしばらく消えなかった。
それから父と二人きりになることに、強い恐怖を覚えるようになった。
それでも、まだ神様は父を見捨てていなかったようで、医師だった父は、
特別養護老人ホームの施設長として、住み込みのほとんど肩書だけの仕事を斡旋してもらい、
しばらくは家族にとって落ち着いた日々が過ぎていった。
しかしまた事態は急変。その頃、父は歩く努力を放棄して車椅子に乗っていた。
その車椅子から落下し、骨折をした。すぐに手術とリハビリができれば回復の見込みがあったにもかかわらず、
父は病院の職員に暴力をふるい転院を余儀なくされ、リハビリも痛みが伴うと暴言を吐き、
結局自力で立ち上がることができなくなった。
その間も姉と私は父のわがままに振り回され、周りの方に頭を下げ、父の言う通りに全てを整え、
精神的にも身体的にも疲れ果てていた。
姉がいてくれたこと、母にこんな思いをさせないですんだこと、世間体。
それだけがあの頃の私を支えていた。
そして、父は介護施設に入った。
週に一度、父に頼まれたものを買い揃えて施設に行く。
話したいこともなく、ただただ義務感と人目を気にして通い続けた。
「ありがとう」と言われることもなかった。
機嫌が悪いと、着いて10分もしないうちに「もう帰っていい」と言われた。
ある日、ベッドから車椅子に移るのを手伝えと言われた。
父の身体に触れることにすさまじい抵抗感を感じた。
本当に父のことが受け入れられなくなっている自分に気がついた。
職員の人を呼び出してもきてもらえず、仕方なく手伝おうとしたが、
うまくできず、父は「痛い!何するんだ!!」と、怒鳴り声をあげた。
泣きたい気分だった。
こんなにやっているのに、ここまでしているのに、父はお礼どころか、笑ってくれることもなくなっていた。
「早く死んでくれないだろうか」
この頃私が検索したワードは「脳梗塞 寿命 透析 余命 あと何年」
でもそんな気持ちに蓋をして、いい娘を演じている自分のことも好きにはなれなかった。
「毎週お父さんのところに通って、えらいわね」と言われるたびに、罪悪感と、自分に対する嫌悪感が増していく。
その頃、「触れる」大切さを習った。
父の体力はどんどんなくなっていき、寝ている時間も増えてきていた。
父と私に残されている時間に限りがあることは明確だった。
このままでは後悔するかもしれない。
父のせいで後悔なんかしたくなかった。
私は父に「触れる」と決めた。
いつものように部屋に入ると、背中を向けて横たわっている父がいた。
病気のせいで体は痩せて、手足はパンパンにむくんでいた、よく右腕が痛いとこぼしていた。
その右の手に触れようと思った。
驚くほど緊張した。
払いのけられたらどうしよう
いつかのように「痛い!」と、怒鳴られたらどうしよう
ひとつ深呼吸をして
父の手に触れた
その瞬間、心がふわっと解けるような感覚を覚え、ただただ父への感謝がこみ上げてきた。
「この人は私の父親なんだ」と全身で思えた。
そして父の目には涙が浮かんだ。
父はずっと辛かったんだ、寂しかったんだ、怖かったんだとその涙は教えてくれた。
それから亡くなるまで、私は会いにいくたびに父の身体に触れ、むくんだ手をさすり、
痩せ細った肩を撫で続けた。
以前と変わらず、父はわがままだったし、機嫌が悪い時もあれば、怒りだすこともあった。
それでも、私は義務感や世間体ではなく、父に会いに行きたかった。
そして、父は亡くなった。
もっと生きていて欲しかったと思えた。
もっと、父の手に触れたかった。
もっと、父の心に触れたかった。
私は「父の娘」として堂々と父の死を悲しみ、晴々とした気持ちで父を見送ることができた。
納骨の日、父のことも、自分のことも、前よりずっと好きになれている自分がいた。
ありがとう・・・
お父さん・・・
あなたの娘でよかったです・・・。
